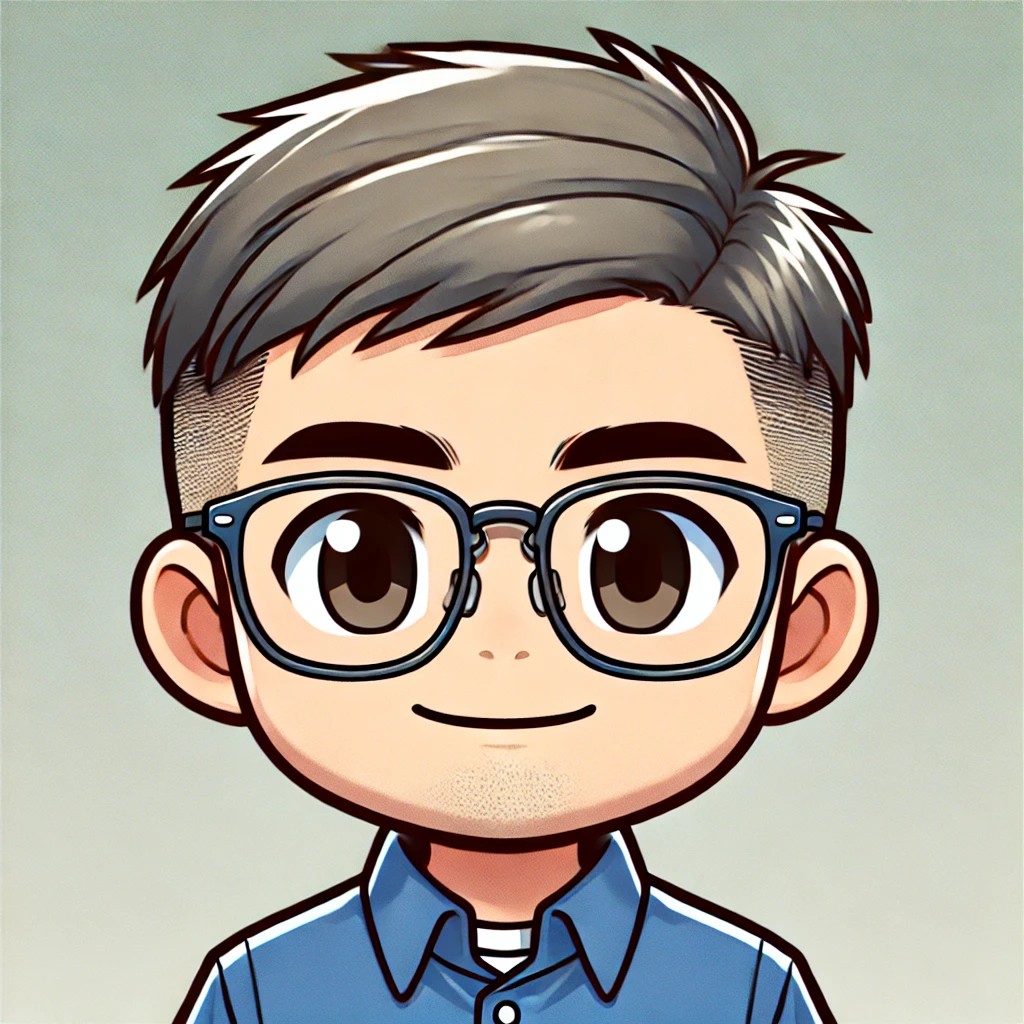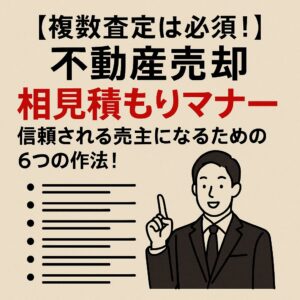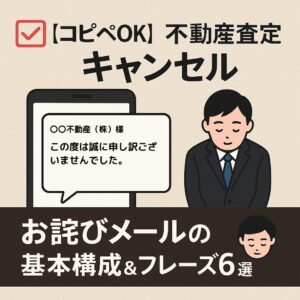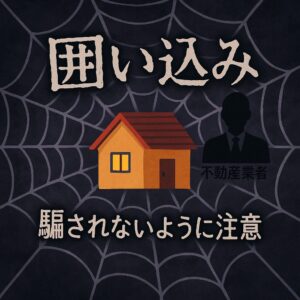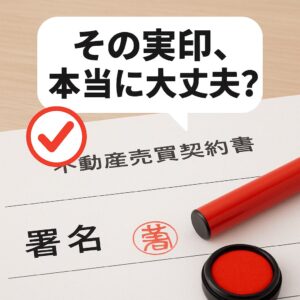実家じまいにかかる費用、少しでも抑えたい…そんなあなたへ
実家を整理し、売却や解体を進める「実家じまい」。
しかし、「どのくらい費用がかかるのか?」「少しでも負担を減らせる補助金はあるのか?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実家じまいに活用できる補助金や助成金の種類、申請方法、注意点を分かりやすく解説します。
自治体によっては解体費用やリフォーム費用の一部を補助してくれる制度もあり、活用すれば数十万円の負担軽減につながることもあります。
こんな疑問や悩みを解決します!
✅ 実家じまいに補助金が使えるの?
✅ どんな補助金があるの?申請条件は?
✅ 申請の流れや手続きは面倒?
✅ 補助金を活用してスムーズに実家じまいを進める方法
実際に、あるご家族は「親が高齢になり、住まなくなった実家の処分を考えていたものの、解体費用が高くてなかなか決断できなかった」と悩んでいました。
しかし、市の解体補助金制度を活用することで、50万円以上の費用負担を軽減でき、スムーズに実家を売却できたのです。
あなたも、適切な補助金を活用することで、費用を抑えながら実家じまいを進めることが可能です。
この記事を読めば、どのような補助金があり、どこで申請できるのかが明確になり、安心して実家じまいを進めるための第一歩を踏み出せます。
無駄な出費を抑え、賢く実家じまいを進めるために、ぜひ最後までお読みください。
実家じまいで失敗しない!知っておくべき基礎知識

実家じまいは、多くの人にとって避けられない課題です。
親が住んでいた家を整理し、売却や解体などの手続きを進めることが求められます。
「実家じまいをスムーズに進めるには、どんな準備が必要なの?」
- 実家じまいとは
- 実家じまいが必要となる背景
- 実家じまいにかかる主な費用
実家を整理する際には、手続きや費用、補助金制度などを理解することが重要です。
まずは、実家じまいの基本から確認していきましょう。
実家じまいとは
実家じまいとは、親が住んでいた家を整理し、処分することを指します。
遺品整理や解体、売却などを進めるために、さまざまな手続きが必要です。
実家じまいする理由には、以下のようなものがあります。
- 親が亡くなり、家を管理する人がいない
- 実家が老朽化し、住むのが難しくなった
- 固定資産税の負担を減らしたい
- 空き家の管理が難しくなった
例えば、親が亡くなった後に家をそのままにしておくと、固定資産税の負担が増えたり、空き家が荒れてしまう可能性があります。
早めに整理を進めることで、費用や手間を抑えながら、スムーズに手続きを完了できます。
実家じまいは時間がかかる作業ですが、計画的に進めることで負担を軽減できます。
 やっちゃん
やっちゃん実家じまいは早めに計画するのが大切!
実家じまいが必要となる背景
実家じまいが必要になる背景には、さまざまな社会的な要因があります。
特に少子高齢化が進む日本では、空き家問題が深刻化しており、多くの人が実家の管理に悩んでいます。
実家じまいが増えている主な理由は以下の通りです。
- 高齢化により、実家を維持できなくなった
- 相続後、誰も住まなくなった
- 空き家のままにすると税負担が増える
- 老朽化で安全面の問題が生じる
例えば、親が住んでいた家をそのままにしておくと、固定資産税の優遇措置がなくなり、税負担が増えてしまうことがあります。
また、老朽化した家を放置すると倒壊の危険があり、近隣住民とのトラブルにもつながる可能性があります。
こうした背景から、実家を適切に整理し、売却や解体を進める人が増えているのです。



実家を放置すると、税金や管理の負担が増えるので注意!
実家じまいの費用は想像以上?費用の全貌を徹底解説!


実家じまいには、さまざまな費用が発生します。
主に解体費用や遺品整理費用、その他の手続き費用がかかります。
実家じまいにかかる主な費用の種類
- 解体費用(木造・鉄筋コンクリート)
- 遺品整理・不用品処分費用
- その他の関連費用(登記・税金など)
実家じまいの費用を抑えるためには、補助金制度や助成金を活用することが重要です。
解体費用
実家をじまいする際、最も大きな費用の一つが解体費用です。
建物の構造や立地条件によって解体費用は異なります。
「実家の解体にはどれくらいの費用がかかるの?」
- 木造住宅の解体費用相場
- 鉄筋コンクリート造の解体費用相場
解体費用は建物の種類や大きさによって大きく異なります。
具体的な相場を確認していきましょう。
木造住宅の解体費用相場
木造住宅の解体費用は、一般的に1坪あたり3万円〜5万円が相場です。
30坪(約100㎡)の家を解体する場合、90万円〜150万円程度の費用がかかります。
木造住宅の解体費用に影響する要因
- 建物の築年数や劣化状態
- 周辺環境(狭小地・住宅密集地など)
- アスベストの有無
- 廃材の処理費用
例えば、築40年以上の古い木造住宅では、廃材の処理費用が高くなるケースがあります。
また、隣家との距離が近い場合は、手作業による解体が必要となり、費用が割高になることもあります。
事前に複数の業者から見積もりを取り、最適な解体方法を選ぶことが重要です。



木造住宅の解体費用は、立地や築年数で変わるよ!
鉄筋コンクリート造の解体費用相場
鉄筋コンクリート(RC)造の解体費用は、1坪あたり5万円〜8万円が相場です。
30坪(約100㎡)の建物を解体する場合、150万円〜240万円程度かかります。
RC造の解体費用に影響する要因
- 建物の階数(2階以上は費用が高くなる)
- コンクリートの強度
- 解体機械の搬入可否
- アスベストの含有状況
例えば、3階建てのRC造建物では、足場の設置や高所作業が必要になり、費用がさらに高くなる傾向があります。
また、解体時に使用する重機を搬入できるかどうかも、費用に大きく影響します。
RC造の解体費用は、業者ごとに見積もりの差が大きいため、慎重に比較検討することが大切です。



鉄筋コンクリート造は解体費用が高めなので、見積もり比較が重要!
解体費用は建物の構造や立地条件によって大きく変わります。
優良業者で安く解体したいなら、「解体無料見積ガイド」で相見積もりをとりましょう!
\ 簡単1分入力!優良解体業者1,000社厳選! /
遺品整理・不用品処分費用
実家じまいでは、解体の前に遺品整理や不用品の処分が必要になります。
思い出の品を整理しながら、必要なものと不要なものを分ける作業には時間と費用がかかります。
「遺品整理や不用品処分にはどれくらいの費用がかかるの?」
- 遺品整理の費用相場
- 不用品処分の費用相場
- 費用を抑えるポイント
遺品整理や不用品処分は、業者に依頼するか自分で行うかで費用が変わります。
具体的な費用の相場や、節約のコツを見ていきましょう。
遺品整理の費用相場
遺品整理の費用は、部屋の広さや作業量によって異なります。
一般的な相場は以下の通りです。
- 1R・1K(約20㎡)…3万円〜8万円
- 1LDK(約40㎡)…5万円〜15万円
- 2LDK(約60㎡)…8万円〜25万円
- 3LDK(約80㎡)…12万円〜40万円
- 一軒家(100㎡以上)…20万円〜50万円
遺品の量が多いほど費用がかさむため、事前に整理しておくと節約につながります。
また、買取可能なものはリサイクルショップや専門業者に売却すると、処分費を抑えられます。



遺品整理は買取サービスを利用すると費用を抑えられるよ!
不用品処分の費用相場
不用品処分の方法には、自治体の粗大ごみ回収、業者による回収、リサイクル業者への買取などがあります。
一般的な処分費用の目安は以下の通りです。
- ソファ・ベッド …3,000円〜10,000円
- タンス・棚 …2,000円〜8,000円
- 冷蔵庫・洗濯機 …5,000円〜15,000円
- テレビ・電子レンジ …1,500円〜5,000円
- エアコン …3,000円〜8,000円
不用品の量が多い場合は、トラック積み放題プランを利用すると費用を抑えられることがあります。
自治体の回収サービスを利用する場合は、事前予約が必要なので注意が必要です。



自治体の粗大ごみ回収を活用すれば、費用を抑えられるよ!
遺品整理や不用品処分は、費用を抑える工夫により経済的な負担を軽減できます。
その他の関連費用
実家じまいでは、解体費用や遺品整理費用のほかにも、さまざまな費用が発生します。
登記や税金の支払い、リフォーム費用など、思わぬ出費がかかることもあります。
「実家じまいにかかるその他の費用には何があるの?」
- 登記や名義変更費用
- 固定資産税・都市計画税
- リフォーム・解体後の整地費用
実家を放置すると税金の負担が増えることもあるため、費用の全体像を把握しておきましょう。
それぞれの費用について詳しく解説します。
登記や名義変更費用
実家を相続した場合、不動産の名義を変更する手続きが必要です。
名義変更しないと売却や解体ができないため、早めに対応しましょう。
登記や名義変更にかかる費用の目安
- 登録免許税 …固定資産評価額の0.4%
- 司法書士報酬 …5万円〜10万円
- 戸籍謄本などの取得費 …数千円
相続登記は義務化されているため、放置すると罰則が科される可能性があります。
専門家に依頼すると手間が省けるので、司法書士などに相談するのも一つの方法です。



名義変更をしないと売却や解体ができないから、早めの対応が大切!
固定資産税・都市計画税
家を相続すると、固定資産税や都市計画税が発生します。
解体した場合、税額が変わることもあるため、注意が必要です。
固定資産税・都市計画税のポイント
- 固定資産税 …土地・建物の評価額の1.4%
- 都市計画税 …評価額の0.3%(市町村により異なる)
- 更地になると固定資産税が最大6倍になる
例えば、家を解体して更地にすると住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増えることがあります。
解体後の土地活用も考えながら、税金の負担を最小限に抑える方法を検討しましょう。



更地にすると税金が高くなるから、事前にシミュレーションしておこう!
リフォーム・解体後の整地費用
実家を解体せずにリフォームする場合、その費用も考慮しなければなりません。
また、解体後の土地を整地する費用も発生します。
リフォーム・整地の費用目安
- 部分リフォーム …50万円〜200万円
- 全面リフォーム …500万円〜1,000万円
- 解体後の整地 …10万円〜30万円
例えば、古い家をリフォームして住む場合、断熱や耐震補強などで高額な費用がかかることがあります。
また、解体後に土地を売却する場合、買い手がつきやすいよう整地しておくと有利です。
次に、解体費用を抑えるための補助金制度について詳しく解説します。
実家じまいの解体費用を大幅節約!使わないと損する補助金5選!


実家じまいの際に発生する解体費用は、高額になりやすいため補助金制度の活用が重要です。
自治体によって異なりますが、条件を満たせば補助金を受け取れる場合があります。
「解体費用を抑えるための補助金にはどんな種類があるの?」
- 老朽空き家解体補助金
- 特定空家指定による補助金
- 耐震診断および耐震改修補助金
- アスベスト除去補助金
- 建て替え建設費補助金
補助金を活用すれば、解体費用の負担を大幅に軽減することが可能です。
それぞれの補助金について詳しく解説します。
老朽空き家解体補助金
老朽化が進んだ空き家を解体する際に利用できる補助金です。
自治体が定める条件を満たすことで、解体費用の一部が補助されます。
支給条件と上限額
- 老朽化が著しい空き家であること
- 倒壊の恐れがあると自治体に認定されること
- 市町村の要件を満たした場合、補助額は最大50万円〜200万円
例えば、築50年以上の空き家で安全上の問題があると判断された場合、解体費用の一部が補助されることがあります。
詳細は自治体ごとに異なるため、事前に確認することが大切です。



自治体の老朽空き家補助金を活用すれば、解体費用を抑えられるよ!
特定空家指定による補助金
特定空家に指定されると、解体費用の補助を受けられることがあります。
特定空家とは、放置することで周囲に悪影響を与える恐れのある空き家のことです。
特定空家の定義と補助金の詳細
- 倒壊の危険がある
- 著しく衛生上の問題がある
- 周囲の景観を著しく損ねている
- 補助金額は自治体によって異なるが、50万円〜200万円程度
例えば、長期間放置されており、近隣から苦情が寄せられている空き家が特定空家に指定されることがあります。
特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置がなくなるため、早めの対応が求められます。



特定空家に指定される前に、自治体の補助金制度を活用しよう!
解体費用を抑える補助金制度はいろいろあります。
次に、耐震診断やアスベスト除去の補助金制度について詳しく見ていきます。
耐震診断および耐震改修補助金
耐震性が不十分な建物の解体や改修する際、耐震診断および耐震改修の補助金を活用できます。
これらの補助金は、建物の安全性向上を目的としており、自治体ごとに内容が異なります。
対象となる建物と補助内容
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物
- 耐震診断費用の一部を補助
- 耐震改修工事費用の一部を補助
- 補助金額や条件は自治体によって異なる
例えば、文京区では、昭和56年5月31日以前に着工された建物の所有者に対し、耐震診断費用の一部を助成しています。
また、多摩市では、耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された木造住宅の所有者に対し、耐震補強計画や耐震補強工事にかかる費用の一部を助成しています。



耐震診断や改修の補助金を利用して、安全な住まいを目指そう!
アスベスト除去補助金
古い建物の解体時には、アスベスト(石綿)が使用されている可能性があります。
アスベストは健康被害を引き起こすため、適切な除去が必要です。
アスベスト使用建物の解体時の補助
- アスベスト調査費用の補助
- アスベスト除去工事費用の補助
- 補助金額や条件は自治体によって異なる
- 事前に自治体へ相談が必要
例えば、埼玉県小川町では、民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度を設けています。
アスベスト除去は専門的な作業が必要なため、信頼できる業者に依頼することが重要です。



アスベスト除去の補助金を活用して、安全に解体を進めよう!
建て替え建設費補助金
解体後に新築を検討する場合、建て替え費用の一部を補助する制度があります。
新しい住宅の建設を支援することで、安全で快適な住まいの整備を促進する目的があります。
解体後の新築建設時の補助内容
- 耐震性の高い住宅の新築補助
- 省エネルギー性能を備えた住宅の補助
- 補助額は自治体により異なる(最大100万円〜300万円)
- 申請前に自治体へ相談が必要
例えば、省エネルギー基準を満たした住宅を建てる場合、補助金を受けられる自治体があります。
新築時のコストを抑えながら、快適な住環境を整えられます。



建て替えの補助金を利用すれば、新築の負担を軽減できるよ!
解体費用を抑えるためには、自治体の補助金を活用することが重要です。
実家じまいの補助金申請!申請の流れを分かりやすく解説


補助金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
申請の流れを理解し、スムーズに手続きを進めましょう。
「補助金申請の手順を知りたい!」
- 申請前の確認事項
- 申請手続きのステップ
補助金を受け取るには、事前の準備が重要です。
詳しい申請の流れを見ていきましょう。
申請前の確認事項
補助金を申請する前に、いくつかの重要なポイントを確認しておきましょう。
条件を満たしていないと、補助金を受け取れない場合があります。
補助金申請前に確認すべきポイント
- 自治体の補助金制度の条件を確認
- 税金の滞納がないかチェック
- 必要な書類を揃える
- 工事開始前に申請を済ませる
例えば、自治体の補助金制度には「工事開始前の申請が必須」というルールがある場合が多いため、工事を始める前に必ず申請しましょう。
また、税金を滞納していると補助金を受けられないことがあるため、事前に確認しておくことが大切です。



申請前に条件を確認し、工事前に手続きを済ませよう!
申請手続きのステップ
補助金を申請する際の一般的な流れを押さえておきましょう。
補助金申請の流れ
- 補助金の対象条件を確認
- 必要書類を準備(見積書・登記事項証明書など)
- 自治体へ申請
- 審査・承認(数週間〜数ヶ月)
- 工事実施後、完了報告を提出
- 補助金の振り込み
補助金の申請から受給までには時間がかかるため、余裕を持って申請することが大切です。



申請から補助金が振り込まれるまで時間がかかるから、早めに動こう!
補助金を利用することで、解体や建て替えの費用を抑えられます。
実家じまいの費用を軽減!補助金以外の節約方法


補助金の利用だけでなく、他の方法を活用することで実家じまいの費用を抑えることが可能です。
解体費用や不用品処分費用をできるだけ抑える工夫をしましょう。
「補助金が使えない場合、どうやって費用を節約できる?」
- 複数の業者からの見積もり取得
- 自分でできる作業の実施
これらの方法を活用し、無駄な出費を防ぎましょう。
複数の業者からの見積もり取得
解体工事や遺品整理を依頼する際には、複数の業者から見積もりを取ることが大切です。
業者によって価格が異なるため、適正な価格で契約するために比較検討しましょう。
見積もりを取る際のポイント
- 3社以上の業者に見積もりを依頼
- 追加費用の有無を確認
- 工事の内容を詳しく確認
- 口コミや評判をチェック
例えば、ある業者は50万円の見積もりでも、別の業者では40万円で対応可能な場合があります。
また、追加費用が発生しないように事前にしっかりと確認しておくことが重要です。



複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格で工事できますよ。
解体工事業者を複数同時に見積もり依頼するなら、以下の「解体無料見積ガイド」を利用すると便利です。
\ 簡単1分入力!優良解体業者1,000社厳選! /
自分でできる作業の実施
業者にすべてを依頼すると費用がかさむため、自分で作業することでコストを削減できます。
自分でできる整理・処分の作業
- 家財道具の整理・処分
- リサイクルショップの活用
- 自治体の粗大ごみ回収を利用
- 庭や家周りの草木の手入れ
例えば、家電や家具をリサイクルショップに持ち込めば、処分費用を抑えつつ買取金額を得られる可能性があります。
また、自治体の粗大ごみ回収を利用すると、民間業者よりも低コストで処分できます。



自分でできる作業を増やすことで、費用を大幅に抑えられるよ!
補助金を活用しつつ、業者選びや自分でできる作業を工夫することで、実家じまいの費用を抑えられます。
実家じまい後の土地、どうする?補助金の活用法と注意点


実家を解体した後の土地をどのように活用するかも重要なポイントです。
放置してしまうと固定資産税が増加する可能性があるため、早めに対策を考えましょう。
「解体後の土地を有効活用するにはどうすればいいの?」
- 土地売却時の特別控除や減税措置
- 固定資産税の変動に注意
- 自治体の空き家バンクや支援制度の活用
土地を売却するか、賃貸として活用するか、選択肢を比較しながら考えていきましょう。
土地売却時の特別控除や減税措置
実家を売却する場合、一定の条件を満たせば税金の軽減措置を受けられます。
特に、譲渡所得3,000万円控除を活用することで、税負担を抑えられます。
譲渡所得3,000万円控除の活用方法
- 相続した家を売却する場合に適用
- 売却益から3,000万円まで非課税
- 適用条件あり(相続後3年以内の売却など)
- 確定申告が必要
例えば、相続した家を1,500万円で売却し、譲渡所得が3,000万円以内なら、譲渡所得税をゼロにできます。
ただし、相続発生から3年以内に売却する必要があるため、スケジュールを意識して進めましょう。



売却時の3,000万円控除を活用すると、税金の負担を大幅に軽減できるよ!
固定資産税の変動に注意
実家を解体すると、固定資産税が大幅に増える可能性があります。
これは、住宅用地の特例が適用されなくなるためです。
解体後の税額変動と対策
- 更地にすると固定資産税が最大6倍に
- 新築や賃貸活用で税負担を軽減
- 売却する場合は早めの手続きが重要
- 市町村の税制優遇措置を確認
例えば、家を解体した後にそのまま放置すると、固定資産税が大幅に増加する可能性があります。
空き地を活用する方法を検討し、税負担を最小限に抑えることが大切です。



解体後に更地のまま放置すると税金が増えるから、早めに活用方法を考えよう!
自治体の空き家バンクや支援制度の活用
自治体が運営する「空き家バンク」や支援制度を活用することで、土地や建物の有効活用が可能です。
空き家バンクの利用方法
- 自治体の空き家バンクに登録
- 購入希望者とマッチング
- 空き家再生や賃貸活用の支援を受ける
- リフォーム補助金の活用
例えば、地方自治体の空き家バンクを利用すると、補助金を受けながらリフォームし、賃貸物件として活用できる場合があります。
活用方法次第で、税金の負担を抑えながら土地や建物を有効に使えます。



空き家バンクを活用すれば、売却や賃貸のチャンスが広がるよ!
実家じまい後の土地活用についてしっかり検討し、最適な方法を選びましょう。
【まとめ】実家じまい、後悔しないために!成功のカギとやるべきこと


実家じまいは、費用や手間がかかる大きな作業ですが、計画的に進めることでスムーズに進行できます。
事前準備や情報収集をしっかり行い、最適な方法を選択しましょう。
本記事のポイントをまとめます。
- 実家じまいの費用を抑えるには補助金の活用が重要
- 解体費用・遺品整理・税金などの費用が発生する
- 補助金には「老朽空き家解体補助金」「耐震改修補助金」などがある
- 補助金を受けるには自治体の条件を確認し、申請が必要
- 解体後の土地活用を検討し、固定資産税の負担を軽減
- 複数の業者から見積もりを取り、コストを最小限に
実家じまいは計画的に進めることで、費用と手間を最小限に抑えられます。
自治体の補助金を最大限活用し、無駄な出費を防ぎながら実家じまいをスムーズに進めましょう。



まずは自治体の補助金制度をチェックしてみましょう。
解体や売却の際には、複数の業者に見積もりを依頼して、最適なプランを選ぶことが大切です。
【よくある質問】実家じまいの補助金に関するQ&A
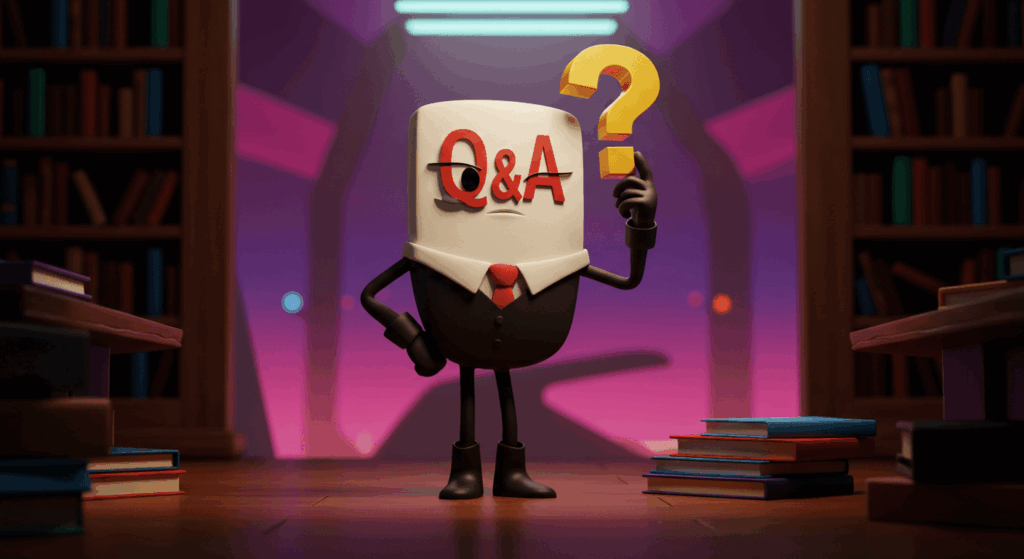
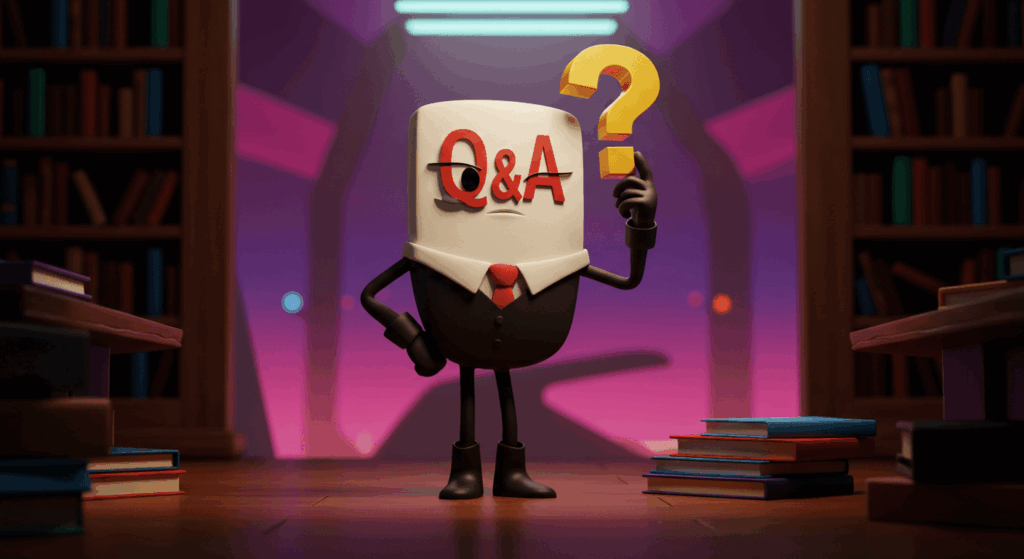
- 実家じまいに補助金は使えるの?
-
自治体によっては、実家の解体費用やリフォーム費用の一部を補助する制度があります。適用条件を満たせば、数十万円の補助を受けることが可能です。
- どんな補助金があるの?申請条件は?
-
主な補助金には、「老朽空き家解体補助金」「特定空家指定による補助金」「耐震診断・改修補助金」「アスベスト除去補助金」などがあります。各自治体ごとに条件が異なるため、事前に確認が必要です。
- 補助金の申請手続きは面倒?
-
補助金の申請には、見積書や登記事項証明書などの書類が必要になります。自治体への申請後、審査を経て承認される流れとなります。手続きに時間がかかることもあるため、早めの準備がおすすめです。
- 補助金を活用してスムーズに実家じまいを進める方法は?
-
まずは自治体の補助金制度を調べ、申請条件を確認しましょう。解体業者や不動産会社とも相談し、補助金を活用できる最適な方法を検討することが大切です。また、複数の業者から見積もりを取ることで、費用を抑えながら進められます。